抗Myelin-associated glycoprotein(MAG)抗体陽性ニューロパチーは、高齢発症、緩徐進行性の左右対称性、遠位有意、感覚有意の脱髄性ニューロパチーで、振戦や感覚性失調を伴うこともあるといわれています。また血液検査ではIgMの上昇、IgM-M蛋白を認める、髄液蛋白は上昇し、MAGやSulphated glucuronyl paragloboside (SGPG)に対する抗体が陽性が特徴といわれています。また治療反応性についてはCIDPで使用される、ステロイド、IVIg、血漿交換の効果は乏しく、リツキシマブによる治療が検討されているかと思います。今回日本人の疫学調査の結果がありましたので、実際どういう特徴なのかどうかについて、ご紹介させていただきます。
Aotsuka Y, Misawa S, Suichi T, et al. Prevalence and clinical profiles of anti‐myelin‐associated glycoprotein neuropathy in Japan: A nationwide survey study of 133 patients. Eur J Neurol. 2024;31:e16249. doi:10.1111/ene.16249, CC BY-NC-ND 4.0
日本における初の全国規模の2021年の疫学調査の結果です。臨床所見、電気生理学的所見についてもまとめられており、本邦での抗MAG抗体陽性ニューロパチーのその特徴を把握するのにとてもよい内容となっています。
推定患者数:353人(95%CI: 287–419)、有病率:0.28/10万人と抗MAG抗体陽性ニューロパチーは稀な疾患という位置づけになっています。
| 抗MAG抗体陽性ニューロパチーの臨床的特徴 | 数値・割合(n=133) |
|---|---|
| 男性の割合 | 78% |
| 発症年齢の中央値(範囲) | 67歳(30~87歳) |
| 初診時の罹病期間の中央値(範囲) | 22か月(0~241か月) |
| フォローアップ期間の中央値(範囲) | 62か月(2~254か月) |
| 血液腫瘍の合併 | 18% |
| └ Waldenströmマクログロブリン血症(合併例中) | 95% |
| └ 多発性骨髄腫(合併例中) | 5% |
| Overall Neuropathy Limitation Score(ONLS) | 上肢:1点(0~4点)、下肢:2点(0~6点)、合計:2点(0~9点) |
| 初回治療前に独歩可能な患者 | 83% |
| 最終受診時に独歩可能な患者 | 73% |
| 診断時の症状(複数回答) | |
| └ 脳神経障害 | 2% |
| └ 筋力低下 | 60% |
| └ 筋萎縮 | 25% |
| └ 腱反射消失(areflexia) | 92% |
| └ 感覚障害 | 74% |
| └ 運動失調(感覚性) | 42% |
| └ 振戦(tremor) | 18% |
| └ 神経因性疼痛 | 50% |
発症年齢中央値67歳と比較的高齢発症でのニューロパチーで、血液腫瘍合併は18%となっています。ONLSの所見からは下肢の障害が強く、長さ依存性の神経障害が考えられます。特徴的所見でいわれている、感覚性運動失調は42%、振戦18%と記載されているほどたくさんある所見ではないようです。
| 抗MAG抗体陽性ニューロパチーの検査所見 | 結果・数値(平均 ± SD または割合)(n=133) |
|---|---|
| 電気生理学的所見(n = 98) | |
| └ 正中神経遠位潜時(ms) | 9.7 ± 5.3 |
| └ 正中神経運動神経伝導速度(m/s) | 36.2 ± 11.2 |
| └ 正中神経CMAP振幅(mV) | 5.8 ± 4.1 |
| └ 正中神経TLI | 0.21 ± 0.09 |
| └ 正中神経感覚神経伝導速度(m/s) | 36.0 ± 11.5 |
| └ 正中神経SNAP振幅(μV) | 3.3 ± 6.3 |
| └ 脛骨神経遠位潜時(ms) | 13.1 ± 7.1 |
| └ 脛骨神経運動神経伝導速度(m/s) | 23.5 ± 9.9 |
| └ 脛骨神経CMAP振幅(mV) | 1.8 ± 3.2 |
| └ 脛骨神経TLI | 0.36 ± 0.15 |
| └ 腓腹神経感覚神経伝導速度(m/s) | 39.0 ± 8.8 |
| └ 腓腹神経SNAP振幅(μV) | 2.2 ± 3.8 |
| IgM型単クローン性ガンマグロブリン血症の合併(n = 129) | 95% |
| 抗体陽性率 | |
| └ MAG+/SGPG+ | 94% |
| └ MAG+/SGPG− | 3% |
| └ MAG−/SGPG+ | 4% |
| 抗MAG抗体力価の中央値(範囲) | 102,400 BTU(1,600~3,276,800) |
| 抗SGPG抗体力価の中央値(範囲) | 819,200 BTU(3,200~819,200) |
| 髄液蛋白(mg/dL) | 平均:111.6(範囲:20~1224) |
| └ 髄液蛋白80 mg/dL以上の割合 | 57% |
| 神経画像所見による神経肥大(異常) | |
| └ 超音波検査での異常 | 15/15例(100%) |
| └ MRIでの異常 | 16/54例(30%) |
電気生理検査では遠位潜時の著明な延長、運動神経伝導速度の中等度な低下を示し、特に血液神経関門(blood–nerve barrier)が脆弱な遠位神経終末が障害されやすく、下肢>上肢でより顕著に障害が強く長さ依存性の脱髄+軸索障害所見です。下Guillain–Barré症候群やCIDPよりも、遠位神経終末障害が顕著である点が特徴的かと思います。IgM型単クローン性ガンマグロブリン血症が95%とほぼ必発で、MAG+/SGPG+が94%と抗体検出率も高くなっています。髄液蛋白についても平均111.6mg/dLで、80mg/dL以上になる割合が57%と診断時の参考になる所見かと思います。神経肥大についてはまだ症例数が少ないかと思いますが、肥大を認める症例もあるようです。
| 抗MAG抗体陽性ニューロパチーの治療と反応率 | 内容・割合 |
|---|---|
| 初回治療までの期間(中央値、範囲) | 25か月(2~317か月) |
| 治療法(複数選択可) | |
| └ 免疫グロブリン静注(IVIg) | 86人(65%) |
| └ 副腎皮質ステロイド | 30人(23%) |
| └ 血漿交換療法(Plasma pheresis) | 15人(11%) |
| └ リツキシマブ(Rituximab) | 42人(32%) |
| └ 化学療法/フルダラビン | 10人(8%) |
| 治療反応率(ONLSで1点以上改善) | |
| └ IVIg | 49% |
| └ ステロイド | 47% |
| └ 血漿交換 | 27% |
| └ リツキシマブ | 64% |
| └ 化学療法/フルダラビン | 20% |
治療については、IVIgが65%と多い結果ですが、初期診断がCIDPとされた可能性が考えられます。次に多かったのはリツキシマブで32%、ステロイドが23%となっています。マクログロブリン血症に関連して、10人(8%)が全身化学療法を受けています。リツキシマブは、この薬剤を使用した患者の43%において初回治療として用いられており、そのうち54%が有効な反応を示し、全体の反応率は64%であり、他の治療群では反応率は50%未満とやはりリツキシマブが最も効果的な治療となっています。また、最も多く使用されたIVIgについては、反応群と非反応群の臨床的特徴を比較した結果、正中神経および腓腹神経のSNAP振幅が非反応群で有意に低いという結果もでています。
Shibuya K, et al. Different patterns of sensory nerve involvement in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy subtypes. Muscle & Nerve. 2022; doi: 10.1002/mus.27530
もう少し電気生理所見を詳しくみたいと思います。上記文献は、CIDPの各病型、抗MAG抗体陽性ニューロパチーの感覚神経伝導検査の違いについて検討されている報告です。
| 指標 | 健常者(N=105) | Typical CIDP (N=68) | Multifocal CIDP (N=27) | Distal CIDP (N=9) | 抗MAG抗体陽性ニューロパチー (N=19) | p-値(typical vs multifocal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別(男:女) | 44:61 | 43:25 | 14:13 | 8:1 | 12:7 | 0.36 |
| 初診時年齢(歳) | 46.1 (17.8) | 47.9 (20.2) | 40.7 (19.3) | 58.3 (16.2) | 66.4 (10.1) | 0.11 |
| 罹病期間(月) | — | 24.0 (50.1) | 52.9 (76.0) | 12.4 (11.1) | 48.7 (53.4) | 0.08 |
| Hughes機能スケール(初診時) | — | 2.0 (1.0) | 1.6 (1.2) | 2.1 (1.1) | 1.7 (0.9) | 0.13 |
| 神経・項目 | 健常者 | Typical CIDP | MultifocalCIDP | Distal CIDP | 抗MAG抗体陽性ニューロパチー | p-値(typical vs multifocal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正中神経 SNAP (μV) | 38.6 (17.9) | 8.4 (10.7) | 14.5 (12.0) | 2.5 (3.6) | 2.2 (1.9) | 0.028 |
| 正中神経 CV (m/s) | 55.6 (6.9) | 40.4 (10.9) | 46.4 (7.4) | 33.0 (8.7) | 29.2 (13.0) | 0.008 |
| 尺骨神経 SNAP (μV) | 38.1 (17.2) | 8.7 (10.0) | 13.8 (11.5) | 1.6 (2.9) | 2.6 (3.3) | 0.055 |
| 尺骨神経 CV (m/s) | 54.5 (4.9) | 40.7 (10.5) | 45.7 (7.7) | 32.3 (7.4) | 34.6 (10.1) | 0.018 |
| 橈骨神経 SNAP (μV) | 40.0 (13.0) | 15.8 (14.3) | 11.9 (12.4) | 10.0 (10.9) | 11.3 (9.5) | 0.26 |
| 橈骨神経 CV (m/s) | 59.4 (4.7) | 48.5 (11.1) | 51.8 (7.8) | 46.8 (11.0) | 50.6 (6.7) | 0.11 |
| 腓腹神経 SNAP (μV) | 18.4 (8.9) | 10.2 (10.3) | 6.9 (8.3) | 6.2 (7.9) | 2.7 (3.9) | 0.13 |
| 腓腹神経 CV (m/s) | 53.7 (6.9) | 46.1 (9.6) | 42.6 (12.2) | 42.2 (9.7) | 41.9 (8.3) | 0.31 |
| パターン | Typical CIDP | Multifocal CIDP | Distal CIDP | 抗MAG抗体陽性ニューロパチー | p-値 (typical vs multifocal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abnormal median normal sural response | 43% | 8% | 33% | 32% | 0.001 |
| Abnormal median normal radial response | 16% | 4% | 33% | 32% | 0.16 |
| Abnormal radial normal sural response | 26% | 13% | 15% | 11% | 0.16 |
抗MAG抗体陽性ニューロパチーでは、SNAP振幅は正中神経、尺骨神経、橈骨神経、腓腹神経で全体的に低下しており、とくに正中神経と尺骨神経で低値となっています。またTypical CIDP同様に「Abnormal median normal sural response」は32%の症例で認められています。
まとめ:抗MAG抗体陽性ニューロパチーは60歳代、男性優位に発症し、下肢>上肢の長さ依存性の脱髄+軸索障害を呈します。日本人の臨床的所見の特徴としては、感覚性運動失調は42%、振戦18%と従来いわれているほど多い所見ではないようです。電気生理検査の特徴としては遠位潜時の著明な延長、運動神経伝導速度の中等度な低下を示し、特に血液神経関門(blood–nerve barrier)が脆弱な遠位神経終末が障害されやすく、下肢>上肢でより顕著に障害が強く長さ依存性の脱髄+軸索障害所見です。感覚神経伝導検査でも全体的なSNAP振幅低下を認め、labo dataではIgM型単クローン性ガンマグロブリン血症、MAGやSGPG抗体が陽性、髄液蛋白上昇を認めます。治療については、従来からいわれているとおり、リツキシマブが最も効果的な治療となっています。


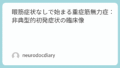
コメント