EGPAではMPO-ANCAが約40%で陽性とされていますが、このANCAによる症状の違いについてはこれまでどのように言われているのでしょうか?
Nat Rev Rheumatol. 2023 Jun;19(6):378-393. doi: 10.1038/s41584-023-00958-w.
上記文献で3つの大規模コホートにおけるANCA陽性およびANCA陰性EGPAの主な臨床的特徴がまとめられています。主症状である喘息と副鼻腔炎に関しては ANCA陽性・陰性の両方に高頻度(90%以上)で認められ、差はないとされています。
| 臨床的特徴 | Comarmond et al. (ANCA+) | Comarmond et al. (ANCA−) | P値 | Sinico et al. (ANCA+) | Sinico et al. (ANCA−) | P値 | Healy et al. (MPO-ANCA+) | Healy et al. (ANCA−) | P値 |
| 喘息 | 93% | 91% | n.s. | 97% | 95% | n.s. | 100% | 100% | n.s. |
| 副鼻腔炎 | 52% | 38% | 0.02 | 77% | 78% | n.s. | 60% | 64% | n.s. |
| 肺病変(いずれか) | 93% | 91% | n.s. | 34% | 60% | 0.02 | 40% | 76% | <0.01 |
| 肺胞出血 | 7% | 3% | n.s. | 20% | 0% | 0.001 | — | — | — |
| 心病変 | 8% | 19% | 0.01 | 6% | 22% | 0.04 | 0% | 38% | <0.01 |
| 消化管病変 | 22% | 23% | n.s. | 20% | 22% | n.s. | 0% | 14% | 0.03 |
| 皮膚病変(いずれか) | 45% | 36% | n.s. | 60% | 48% | n.s. | 67% | 62% | n.s. |
| 紫斑 | 29% | 20% | n.s. | 26% | 7% | 0.02 | 53% | 40% | n.s. |
| 末梢神経障害(いずれか) | 63% | 44% | <0.01 | 71% | 60% | n.s. | 73% | 42% | 0.02 |
| 多発単神経炎 | 55% | 39% | <0.01 | 51% | 24% | 0.01 | — | — | — |
| 中枢神経病変 | 7% | 4% | n.s. | 17% | 12% | n.s. | 20% | 13% | n.s. |
| 腎病変 | 27% | 16% | 0.02 | 51% | 12% | <0.001 | 33% | 16% | n.s. |
| 生検での血管炎所見 | — | — | — | 76% | 32% | <0.001 | 81% | 61% | n.s. |
まとめると
| 分類 | 特徴的な症状 | 傾向 |
| ANCA陽性(約40%) | – 糸球体腎炎 – 末梢神経障害(多発単神経炎) – 紫斑(皮膚血管炎) – 肺胞出血 | 血管炎型の特徴が強い 病理:壊死性血管炎が中心 再発率が高い |
| ANCA陰性(約60%) | – 心筋炎・心筋症 – 肺浸潤(浸潤影・結節) – 胃腸炎 | 好酸球浸潤型の傾向が強い 病理:好酸球性肉芽腫や浸潤が主体 心病変の頻度が高く、死亡リスクが高い |
ただし、臨床的に重複する部分も少なくなく、診断においてはあらゆる症状を総合的に考慮する必要があるとされています。
それでは神経障害についてはどうでしょうか?EGPAでは日本の疫学データでは93%もの症例で神経症状を呈していたとされています(Mod Rheumatol. 2014 Jul;24(4):640-4.)。それではANCAの有無によって神経病理はどうなっているのでしょうか?
Neurology. 2020;94(16):e1726-e1737. doi: 10.1212/WNL.0000000000009309.
対象:名古屋大学からの報告です。82症例のEGPAで、腓腹神経生検を全例実施されています。
結果:
| 項目 | MPO-ANCA陽性 n=27 | MPO-ANCA陰性 n=55 |
| 割合 | 32.9% | 67.1% |
| 初発症状(上肢) | 44.4%(多い) | 14.6% |
| CRP, mg/dl | 6.5(有意) | 4.1 |
| 腎病変 | 11.1%(やや多い) | 1.8% |
| 消化器病変 | 0.0% | 9.1%(やや多い) |
| 正中神経CMAP | 低下(有意) | 保たれている |
| 有髄線維密度 | 低下(有意差なし) | 低下(有意差なし) |
| 血管構造破壊の頻度 | 55.6%(有意に多い) | 10.9% |
| フィブリノイド壊死 | 40.7%(有意) | 5.5% |
| 好酸球の血管内浸潤, n/vessel | 0.18 | 0.53(有意に多い) |
| 好酸球の内皮接着, n/vessel | 0.09 | 0.30(有意に多い) |
| 好酸球で内腔が占拠された血管 | 0.7〜0.2% | 3.2〜1.1%(有意に多い) |
| 神経内膜への好酸球浸潤 | 7.4%(少ない) | 41.8%(有意に多い) |
| 障害される血管径 | 169μm(大径) | 13μm(小径) |
障害される血管についてはMPO-ANCA陽性例では血管構造の破壊(=典型的な血管炎)は中等度から大きめの血管(169μm)で起きていて、一方、MPO-ANCA陰性例では小血管(10〜13μm)で好酸球が内腔を詰まらせて閉塞している所見でした。このことから、ANCA陽性EGPAでは大血管の破壊による虚血が主因、ANCA陰性EGPAでは小血管の好酸球閉塞による虚血が主因と考えられている結果となっています。
治療については、上記reviewに、“There is still no evidence that different phenotypes (such as ANCA-positive versus ANCA-negative) necessitate different approaches.”
ANCA陽性と陰性といった表現型に応じて異なる治療アプローチを取るべきというエビデンスは現時点では存在しないという記載があり、治療については現状では、ANCAの区別で治療内容を決定するということは難しいようです。
まとめ:EGPAにおけるANCAの測定の意義としては治療については、まだエビデンスが不足している分野となっていて治療の選択肢を考えるときには、臓器障害の重症度やFive-Factor Scoreなどの臨床的因子に基づいて決定すべきと考えられています。また臨床表現型の違いの認識、EGPA診断補助としての役割、最後に予後に関する示唆として、ANCA陰性患者は心障害の頻度が高く、全体的な予後はやや不良、一方で、ANCA陽性患者は再発率が高い傾向にあることを参考にフォローできることがメリットといえるでしょうか。


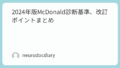
コメント