パーキンソン病のウェアリングオフのデバイス治療として、皮下注投与のfoslevodopa/foscarbidopa(FLFCI)が全国的に広く行われるようになっていますが、レボドパによる末梢神経障害というものはご存じでしょうか?
一般的に、レボドパ治療(特にレボドパ・カルビドパ経腸用液療法:LCIG)に関連する多発ニューロパチーは、最大42%の頻度で報告されており、うち約3分の1は急性または亜急性発症で、90%が感覚優位の軸索障害型を呈する末梢神経障害です。ビタミンB6、B12、葉酸の欠乏や高ホモシステイン血症・メチルマロン酸上昇が関与するとされています。以下にFLFCIで生じたと考えられる末梢神経障害のケースレポートがありましたので診療の参考になれば幸いです。
Valli A, Scheperjans F. Subacute Painful Axonal Polyneuropathy Associated with Foslevodopa/Foscarbidopa Subcutaneous Infusion in Advanced Parkinson’s Disease. Movement Disorders. 2025. DOI: 10.1002/mds.30297, CC BY-NC-ND 4.0
症例は71歳女性、6年間のパーキンソン病(PD)罹患歴があり、複数の抗パーキンソン薬を内服してもオフ時間が約8時間あるということで、FLFCI皮下注療法に切り替えしています。日中0.81 mL/h、夜間0.65 mL/hの投与量(LED:3360mg/日)で良好な効果を得ていましたが、治療開始から7か月後、足部のしびれと疼痛が出現し、2か月で手指にも波及。診察では、6か月間での5kgの体重減少、遠位腱反射の左右対称な減弱、温度感覚および振動覚の低下、さらに膝から下および指先にかけてのアロディニア(異痛症)を認めました。電気生理検査は、感覚優位の重度の軸索性多発ニューロパチーと、慢性的な運動線維の障害を認めましたが、脱髄所見はなく、血液検査ではビタミンB6 41nmol/L(基準値51-183)と葉酸 8.1nmol/L(基準値 >8.8)の欠乏、ビタミンB12は正常、ホモシステイン57.0 µmol/L(基準値 0-10)は著明に上昇がありました。他の原因(糖尿病、腫瘍性疾患、感染症、自己免疫性疾患など)は否定的でした。
治療と経過
ビタミンB6、B12、葉酸の補充およびデュロキセチン投与により、FLFCIの中止なしに2週間で症状が改善。ホモシステイン値も改善した(21 µmol/L)。
まとめ
今回の報告症例は、日中0.81 mL/hと日本ではあまり使用されないような高容量のFLFCIになっていまました。このような高容量で使う症例はあまり多くはないかもしれませんが、FLFCIは、ビタミン欠乏およびホモシステイン上昇を介して、亜急性の感覚優位軸索性PNPを引き起こす可能性があり、FLFCIは腸管吸収を介さないため、レボドパ代謝によるビタミン消費が主因と推察されます。ビタミンB12、B6、葉酸、ホモシステインなどの定期的モニタリング、早期補充が推奨されます。

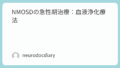
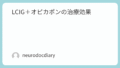
コメント