脊髄梗塞の大半は前脊髄動脈領域(ASA)に発生しますが、稀に後脊髄動脈(PSA)領域に梗塞をきたすこともあります。前回のreviewに続いて、今回はPSA領域の脊髄梗塞の臨床的特徴についてみていきたいと思います。
Zalewski NL, Rabinstein AA, Wijdicks EFM, et al. Spontaneous posterior spinal artery infarction: An under-recognized cause of acute myelopathy. Neurology. 2018;91(9):414–417. doi:10.1212/WNL.0000000000006084
本研究では、1997~2017年にMayo Clinicで診断された前脊髄梗塞133例中PSA梗塞15例(11%)を後ろ向きに検討し、その臨床像、画像所見、転帰を明らかにすることを目的としています。
年齢中央値:64歳(36~75歳)、女性:60%、
14/15例(93%)で血管障害リスクをもっていました:(脂質異常症73%、喫煙40%、高血圧40%、糖尿病7%、心房細動7%)
臨床的特徴
| 項目 | 症例数/割合 |
|---|---|
| 発症から最大障害までの時間 ≤4時間 | 12例(80%) |
| 同 ≤6時間 | 1例(7%) |
| ≥24時間(段階的悪化) | 2例(13%) |
| 感覚障害(後索優位) | 15例(100%) |
| 筋力低下 | 11例(73%) |
| 発症時の疼痛 | 9例(60%) |
| 排便・排尿障害 | 8例(53%) |
| 感覚性運動失調 | 7例(47%) |
症状のピークまでが4時間以内、PSA領域の後索障害に伴う感覚障害や感覚性運動失調以外にも、筋力低下や膀胱直腸障害を呈しています。また前回のreviewでも取り上げましたが60%の症例で発症時の疼痛があることも特徴的かと思います。後索をこえた所見がでる理由としては、脊髄血管支配の重なりや多様性、初期の前脊髄動脈(ASA)虚血の併存、あるいは浮腫による可能性が考えられています。
髄液所見
| 項目 | 症例数/割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 蛋白上昇(>35 mg/dL) | 7例(47%) | 中央値:59(43–116)mg/dL |
| 白血球増加 | 0例(0%) | – |
| OCB陽性 | 0例(0%) | – |
MRI所見
| 項目 | 症例数/割合 | 備考・中央値(範囲) |
|---|---|---|
| 脊髄病変 | 15例(100%) | 1日(0~38日) |
| 初回MRI正常(発症後0–1日) | 5例(33%) | – |
| 非連続性T2高信号 | 9例(60%) | – |
| 長大病変(3椎体以上) | 9例(60%) | – |
| Gd造影効果 | 6例(40%) | 検査日:14日(6~21日)後 |
| 脊髄軟化(1か月以降) | 6例(40%) | – |
| 椎体梗塞 | 3例(20%) | 発症後4日(1~19日)で確認 |
| 拡散強調像での制限 | 3例中2例(67%) | 発症後2日(1~3日)で確認 |
| 頸髄病変 | 8例(53%) | – |
| 胸髄病変 | 7例(47%) | – |
髄液所見は発症何日目に実施したかという記載はありませんが、蛋白細胞解離を示ることが約50%で認めることがわかります。MRI所見では発症当日は33%が偽陰性となり、DWIでの評価が行われている症例数は少ないですが67%で認めています。またT2高信号病変が3椎体以上になることが60%ありますが、一方で不連続性が60%に認められるという所見です。椎体梗塞の頻度は少なく20%となっています。また、頸髄病変の頻度が高く、血管解離や閉塞などMRAによる評価も必要となってきます。
治療
| 項目 | 内容・人数 | 補足 |
|---|---|---|
| 誤診により免疫治療を受けた患者 | 11例(73%) | ステロイド:10例、IVIg:4例(重複あり) |
| 血栓溶解療法(t-PA) | 1例 | 発症4時間後に施行、急性期の効果なし/2か月後にAFOで歩行可能に |
| 最終的な治療方針 | 血管リスクの管理と抗血小板療法 | SCIと確定後に開始 |
治療については、免疫治療(ステロイド、IVIg)が実施されている割合が比較的たっかう73%、t-PAも使用されている症例が1例ありました。また診断確定後はリスク管理、抗血小板薬の使用となっています。
転機
| 項目 | 内容・人数 | 補足 |
|---|---|---|
| フォローアップ期間の中央値 | 8か月(範囲:1~71か月) | – |
| 歩行可能(補助具なし) | 8例(53%) | – |
| 歩行補助具が必要 | 6例(40%) | 杖などの使用を含む |
| 非歩行 | 1例(7%) | – |
| 症状の改善あり | 13例(87%) | – |
| 症状改善なし | 2例(13%) | うち1例は追跡期間1か月未満 |
| 新たな神経学的イベントの発生 | 0例(0%) | – |
約半数の症例が補助具なしの歩行が可能となり、補助具使用での歩行も40%と、合わせると93%の症例で歩行可能になる割合が高いという結果となっていました。
Tan YJ, Teo TL, Yeo CL, et al. Clinical Features and Outcomes of Posterior Spinal Artery Infarction: A Systematic Review. Research Square (2023). doi:10.21203/rs.3.rs-3645041/v1, CC BY 4.0
つぎに紹介する文献は、後脊髄動脈梗塞(Posterior Spinal Artery Infarction, PSAI)の臨床的特徴と転帰を整理し、歩行障害との関連因子を明らかにすることを目的として、過去30年の文献を系統的にレビューしたものです。
対象期間:1993年~2023年6月、データベース:PubMed, Google Scholarから、最終的に40症例(33報)を分析対象としています。
年齢中央値:55歳(範囲19–84)、男性23例、女性17例
心血管危険因子あり:53%(高血圧76%、喫煙38%、脂質異常症29%、糖尿病24%)
神経所見
| 項目 | 症例数/割合 |
| 疼痛 | 19/48%(そのうち15/19例, 79%は発症初期) |
| 感覚障害 | 38/97% |
| 後索障害 | 28/74% |
| 脊髄視床路障害 | 13/34%:同側1例、対側5例、両側7例 |
| 運動障害 | 27/69% |
| 膀胱障害 | 13/33% |
| Brown-Sequard症候群(完全・部分) | 14/36% |
| 顔面感覚障害(C1/延髄病変を伴う) | 5/13% |
このreviewでも発症時の疼痛がやはり多く、後索障害以外にも錐体路、脊髄視床路におよぶ障害が合併することが30-60%でみられるようです。また膀胱直腸障害やBrown-Sequard症候群を呈することも報告されています。
病変の分布
頚髄病変が大多数(73%):40例中29例で頚髄に病変を認め、そのすべてが高位頚髄(C1–C4)に及んでいました(28/28例、100%)。
最も多い病変レベル:C1(61%)
以下、頻度順に
- C2:48%
- C3:33%
- C4:30%
- C5:19%
- C6:15%
- C7:11%
胸髄病変は32%(12/37例): 頚髄+胸髄の合併はごくわずか(1例のみ)。
病変の左右差: 片側性病変が多数(64%)、 左側が右側の約2倍(左68%、右32%)
病変の長さ: 多くは短い病変だが、3セグメント以上に及ぶ長い病変も40%に認められた
周囲構造への波及は稀
- 延髄:9例
- 小脳:4例
- 椎体:3例
誘因
明確な誘因がある症例は23例(57%)となっています。
- 外傷性誘因(8/23例、35%): 荷物運搬、シャッターの上げ下げ、交通事故、頭部外傷を伴う転倒など
- 非外傷性誘因(7/23例、30%): 血管内治療(動脈瘤、硬膜動静脈瘻、椎骨動脈や後下小脳動脈・脊髄動脈の狭窄に対する治療)
- その他の誘因(少数例): 洗顔、階段昇降、雪かき、頚部の過伸展など多様
主な原因:
- 椎骨動脈解離(VAD):8例(20%)
- 血管内治療の合併症:7例(18%):VADの治療後3例、dAVF治療後2例、椎骨動脈狭窄治療1例、椎骨動脈瘤治療1例
- 塞栓性疾患(まれな例):線維軟骨塞栓、僧帽弁線維束、卵円孔開存
治療
- 記載があった28例中
- 抗血小板薬使用:18例(64%)
- 抗凝固薬使用:8例(29%):静注ヘパリン、ウロキナーゼ、皮下注LMWH、経口ワルファリン/リバロキサバン
- ステロイド高用量使用:5例(18%)→ 少なくとも3例はメチルプレドニゾロンの静注
転機
- 報告のばらつきあり:アウトカム評価の記載が不完全で、時点も不統一(退院時~2年後まで)
- 全体
- 死亡:3例(34例中9%)
- 歩行可能:28例(34例中82%)
- 歩行補助が必要だった者:28例中8例(29%)
歩行転機に影響する因子
| 比較項目 | 歩行困難群(n=6) | 歩行可能群(n=28) | 有意差(p値) |
|---|---|---|---|
| 年齢(中央値) | 67歳(52–84) | 56歳(28–79) | 0.055(傾向あり) |
| 性別(男性) | 33% | 57% | 有意差なし |
| 心血管危険因子あり | 67% | 46% | 有意差なし |
| 発症前の外傷 | 50% | 11% | 0.053(傾向あり) |
| Brown-Sequard症候群(部分含む) | 50% | 37% | 有意差なし |
| 疼痛の有無 | 67% | 43% | 有意差なし |
| 筋力低下あり | 100% | 64% | 有意差なし |
| 頚髄梗塞 | 67% | 71% | 有意差なし |
| 胸髄梗塞 | 33% | 29% | 有意差なし |
| 両側病変 | 33% | 37% | 有意差なし |
| 3セグメント以上の病変 | 83% | 33% | 0.062(傾向あり) |
| 延髄または小脳の梗塞合併 | 33% | 25% | 有意差なし |
| – 延髄病変あり | 33% | 21% | 有意差なし |
| – 小脳病変あり | 17% | 11% | 有意差なし |
| 原因不明 | 33% | 21% | 有意差なし |
| 椎骨動脈解離 | 0% | 21% | 有意差なし |
| 血管内治療合併症 | 0% | 25% | 有意差なし |
P<0.05となる項目はいずれもありませんでしたが、高齢・外傷歴・長い病変(3セグメント以上)は、歩行困難(非自立)と関連する傾向がみられています(p≒0.05付近)。また、性別、危険因子、病変の左右・部位、症状(痛み・筋力低下)、病因(原因不明、VAD、血管内治療)も歩行予後に有意な関連はみられませんでした。
後脊髄動脈領域の脊髄梗塞の臨床的特徴のまとめ
およそ50-60歳代に発症する疾患、高血圧などの血管障害リスクを持つことが多く、発症時の疼痛がみられ、症状のピークまでが4時間以内が病歴聴取でのポイントになります。また、診察所見では頚髄>胸髄の障害が多く、PSA領域の後索障害以外にも脊髄視床路、錐体路障害を合併することもあります。髄液では蛋白細胞解離となることがあり、MRIでは発症から1日は偽陰性となることが多く、T2高信号は3椎体以上となったり不連続性の病変を呈することがあります。急性期治療は抗血栓療法がおこなわれることが多く、臨床転機としては、錐体路障害が顕著になることは少ないため、歩行可能となる症例は多いため、疑わしい症例はしっかりと診断して、適切なリハビリテーションへつなげることが重要と思います。
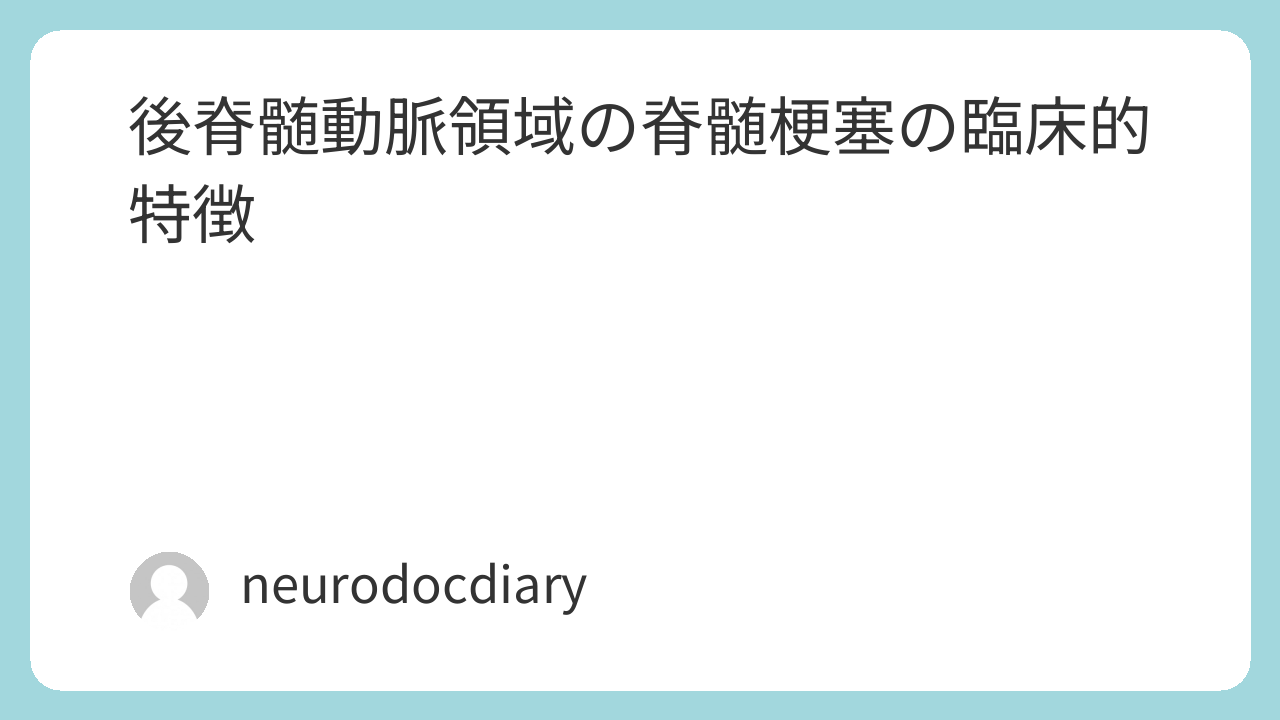


コメント